
ステンレスパイプを用いた部品製造において、「材料費が高騰している」「切削加工ではコストが合わない」「薄肉形状の精度が出ない」といった課題にお悩みではありませんか?
難削材であるステンレス(SUS)は、一般的な加工方法では歩留まりが悪く、量産時のコスト高を招きやすい素材です。しかし、製造プロセスを「削る」から「冷間鍛造で成形する」へ転換することで、劇的なコストダウンと品質向上を実現できる可能性があります。
本記事では、ステンレスパイプ加工が難しい技術的理由から、量産における課題、荻野工業ならではの「工法転換(VA/VE)」による解決策、そして実際の成功事例までを詳しく解説します。
ステンレスパイプ加工・製造が「難しい」と言われる理由
ステンレスパイプ(SUSパイプ)を用いた部品製造は、自動車部品や産業機器、センサー部品など多岐にわたる分野で求められていますが、その加工難易度は極めて高いとされています。多くの調達担当者や設計エンジニアが直面する「コスト高」「納期遅延」「品質不良」といった課題は、主に「素材特性」と「形状特性」の2点に起因します。ここでは、なぜステンレスパイプの加工が難しいのか、その技術的背景を解説します。
ステンレス(SUS)の素材特性と加工硬化
ステンレス鋼(特にオーステナイト系のSUS304やSUS316)は、耐食性や強度に優れる一方で、金属加工においては代表的な「難削材」として知られています。その最大の要因は「加工硬化」と「熱伝導率の低さ」です。
加工硬化とは、切削やプレスなどの力が加わった部分が硬くなる現象です。ステンレスは特にこの傾向が強く、一度刃物を当てて硬化した表面に対し、再度加工を行おうとすると工具の摩耗が激しくなり、最悪の場合は工具破損を招きます。量産加工においては、頻繁な工具交換が必要となるため、ダウンタイム(機械停止時間)が増加し、製造コストを押し上げる主要因となります。
また、ステンレスは熱伝導率が低いため、加工時に発生する切削熱が切り屑や母材に逃げにくく、工具の刃先に熱が集中します。これが「構成刃先(溶着)」を引き起こし、加工面の精度低下やバリの発生につながります。したがって、ステンレスパイプの加工には、適切な切削油の選定や、熱と硬化をコントロールする高度なノウハウが不可欠です。
パイプ形状特有の課題(歪み・真円度・バリ)
素材自体の難しさに加え、「パイプ(中空形状)」であること自体が加工のハードルをさらに上げます。中実の丸棒と異なり、パイプ材は肉厚が薄いため、加工時のチャッキング(固定)圧力や切削抵抗によって容易に「歪み」が生じます。
例えば、旋盤加工のためにチャックで強く掴むと、その圧力でパイプが楕円に変形してしまい、加工後にチャックを外すと元に戻ろうとして真円度が出ないというトラブルが頻発します。これを防ぐために把持力を弱めれば、今度は加工中にワークが滑ったり、ビビリ振動が発生して表面粗さが悪化したりします。特に「薄肉パイプ」と呼ばれる領域では、このジレンマが顕著です。
さらに、パイプ切断や穴あけ加工時に内径側に発生する「バリ」の処理も深刻な課題です。内径のバリは除去が難しく、流体制御バルブやセンサー部品などの場合、微細なバリの残留が致命的な機能欠陥(液漏れや作動不良)を引き起こします。
このように、ステンレスパイプの加工・製造には、難削材を扱う技術と、剛性の低い中空形状を高精度に仕上げる技術の両立が求められるのです。
一般的なステンレスパイプ加工方法と量産時のデメリット
ステンレスパイプ部品を調達する際、多くの設計図面では「パイプ材からの切削」や「パイプの曲げ・溶接」が指定されています。
試作や小ロット生産(数十個~数百個)の段階ではこれらの工法が最適解となる場合も多いですが、月産数千個、数万個という量産フェーズに入ると、コスト構造や生産能力(キャパシティ)の面で大きなデメリットが生じることがあります。ここでは主要な2つの工法について、量産時の課題を整理します。
切削加工(旋盤・マシニング)による「材料ロス」の壁
NC旋盤やマシニングセンタを用いた切削加工は、高い寸法精度と形状自由度を実現できる最もポピュラーな工法です。市販のステンレスパイプ材(素管)や丸棒をチャッキングし、刃物で削り出して製品形状に仕上げます。
しかし、量産時における最大のデメリットは「材料歩留まりの悪さ(材料ロス)」と「加工時間の長さ」です。
特に、フランジ形状や段付き形状を持つパイプ部品を「丸棒(中実材)」や「肉厚パイプ」から削り出す場合、製品として残る部分よりも、切り屑(スクラップ)として捨ててしまう部分の方が多くなるケースが珍しくありません。ステンレス材(SUS304、SUS316等)は材料単価が高騰傾向にあるため、材料の50%~70%を切り屑にしてしまう切削加工は、原価低減の大きな足枷となります。
また、前述した通りステンレスは難削材であるため、高速で削ることが難しく、サイクルタイム(1個あたりの加工時間)短縮には限界があります。量産数をこなすためには設備台数を増やす必要があり、それが償却費や加工費として製品単価に跳ね返ってきます。「数量が増えても単価があまり下がらない」という場合、この工法上の限界に直面している可能性が高いと言えます。
溶接・曲げ加工における「品質バラツキ」とリードタイム
配管部品などで用いられる「曲げ」や、フランジ等の別部品を接合する「溶接」も一般的な工法です。
溶接加工における量産時の課題は、「熱影響による品質リスク」と「工程分断による管理コスト」**です。ステンレスの溶接は、熱による鋭敏化(耐食性の低下)や歪みが発生しやすく、気密性が求められるバルブや流体部品においては、全数検査などの厳しい品質管理が必要となりコストを押し上げます。
また、曲げ加工においては「スプリングバック(跳ね返り)」の制御が難しく、ロットごとの材料特性のバラつきがそのまま製品精度のバラつきに直結します。
さらに、これらは「切断→曲げ→洗浄→溶接→仕上げ」といった複数の工程(場合によっては複数の協力工場)をまたぐことが多く、横持ち(移動)コストやリードタイムが肥大化しがちです。一貫生産できない体制での量産は、納期遅延のリスクも高めてしまいます。
ステンレスパイプ加工のコストダウンを実現する「工法転換(VA/VE)」
前述した「切削加工の材料ロス」や「多工程によるコスト増」といった課題を解決する最も有効な手段が、製造プロセスそのものを見直す「工法転換(VA/VE提案)」です。特に月産数千個以上の量産部品においては、既存の図面通りの工法(パイプ材からの切削など)に固執せず、「形を作る技術」を最適化することで、品質を維持したまま20%~50%以上のコストダウンが可能になるケースがあります。
「削る」から「成形する」へ。冷間鍛造によるパイプ部品製造
コストダウンの鍵を握るのが、金属を叩いて成形する「冷間鍛造(Cold Forging)」技術の活用です。
一般的なステンレスパイプ加工が「パイプ材を購入し、不要な部分を削り落とす(除去加工)」であるのに対し、冷間鍛造によるパイプ部品製造は「コイル材(線材)から必要な形状を塑性変形で作る(付加加工)」というアプローチを取ります。
具体的には、安価なコイル材を切断し、常温下で数トンの圧力をかけて金型内で圧縮・成形します。この工法の最大のメリットは「材料歩留まりの圧倒的な向上」です。中実の線材から深絞りや後方押出しによってパイプ形状(中空形状)を成形するため、切り屑(スクラップ)がほとんど出ません。
高価なステンレス材において、材料をほぼ100%製品に転化できることは、原価低減に直結します。また、鍛造加工は「ファイバーフロー(金属組織の流れ)」を切断しないため、切削品に比べて製品の機械的強度が向上するというメリットもあります。
「冷間鍛造 × 高精度切削」の複合加工という選択肢
もちろん、冷間鍛造だけで全てのステンレスパイプ部品が完成するわけではありません。鍛造は複雑なアンダーカット形状や、ミクロン単位の厳しい寸法公差を出すことには不向きな側面があります。
そこで私たちが提案しているのが、「冷間鍛造」と「高精度切削」を組み合わせた複合加工です。
- ベース形状の作成(冷間鍛造)
:材料ロスの多い「大まかな形状(ニアネットシェイプ)」や「パイプ穴」までを、高速かつ材料レスで成形します。 - 仕上げ加工(高精度切削)
:シール面や嵌合部など、特に精度が必要な重要箇所のみをNC旋盤やマシニングで仕上げます。
この「いいとこ取り」を行うことで、オール切削に比べて加工時間を大幅に短縮しつつ、全数切削保証と同等の高精度な製品を提供することが可能になります。特に、「フランジ付きパイプ」や「段付きスリーブ」のように、丸棒から削り出すと捨て代が多くなる形状ほど、この工法転換の効果は劇的です。
荻野工業(量産精密金属加工コストダウンセンター)の強み
このような工法転換を実現するには、単一の加工技術だけでなく、素材の選定から金型設計、切削、熱処理までを統合的に判断するエンジニアリング能力が不可欠です。
荻野工業(量産精密金属加工コストダウンセンター)は、冷間鍛造機(パーツフォーマー)と高精度NC旋盤の双方を自社保有し、一貫生産体制を敷いています。「この形状なら、ここまでを鍛造にして、ここからを切削にすれば安くなる」といった、図面段階からのVA/VE提案(価値分析・価値工学提案)を行える点が、単なる加工受託メーカーとの決定的な違いです。
お客様の要求スペック(真円度、同軸度、面粗度など)を深く理解した上で、最適な「製造のレシピ」を設計し、量産コストの最小化を実現します。
ステンレスパイプ加工に関するよくある質問
Q. ステンレスパイプの冷間鍛造(工法転換)は、どのくらいのロットからコストメリットが出ますか?
A. 形状やサイズによりますが、一般的には月産3,000個~10,000個以上の量産において、切削加工からの工法転換によるコストダウン効果(20%~50%削減など)が顕著になります。初期費用として金型費が必要になりますが、材料費削減と加工速度向上により、数ヶ月から半年程度で償却できるケースが多いです。
Q. どのくらいの肉厚(薄肉)まで対応できますか?
A. 製品形状にもよりますが、肉厚0.5mm前後の薄肉パイプ形状の成形実績がございます。薄肉品は切削では歪みが出やすいですが、冷間鍛造であれば金型内で高圧成形するため、安定した品質を維持できます。詳細な限界値については、製品の長さや径とのバランスによりますので、図面を拝見した上で回答させていただきます。
Q. 既存の図面は「切削」指示ですが、そのまま相談しても良いですか?
A. はい、問題ございません。荻野工業(量産精密金属加工コストダウンセンター)では、お客様の図面をもとに「機能を満たしたまま、より安く作るための形状変更(VA/VE)」をご提案します。「ここをR形状にすれば鍛造化できる」「この公差なら成形のみで対応可能」といった専門的な代案を提示いたします。
ステンレスパイプの量産・加工依頼なら荻野工業へ
ステンレスパイプ部品の加工において、「コストが下がらない」「品質が安定しない」という課題の多くは、工法(作り方)のミスマッチに原因があります。特に量産品においては、既存の切削加工やパイプ材利用に固執せず、「冷間鍛造」や「複合加工」といった視点を取り入れることが、競争力強化への近道です。
荻野工業(量産精密金属加工コストダウンセンター)は、ステンレスをはじめとする難削材の加工ノウハウと、設計段階から入り込むVA/VE提案力を強みとしています。「今の図面のままでいいのか?」「もっと安く作る方法はないか?」とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。貴社の製品に最適な、高品質・低コストな製造プロセスをご提案いたします。
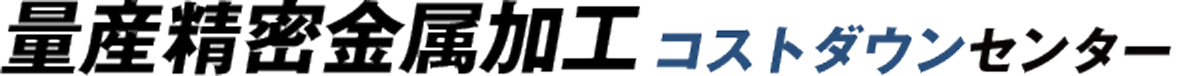
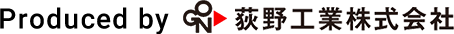
 0297-48-1421
0297-48-1421
 ご相談・お問合せ
ご相談・お問合せ
 技術資料ダウンロード
技術資料ダウンロード